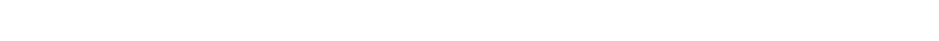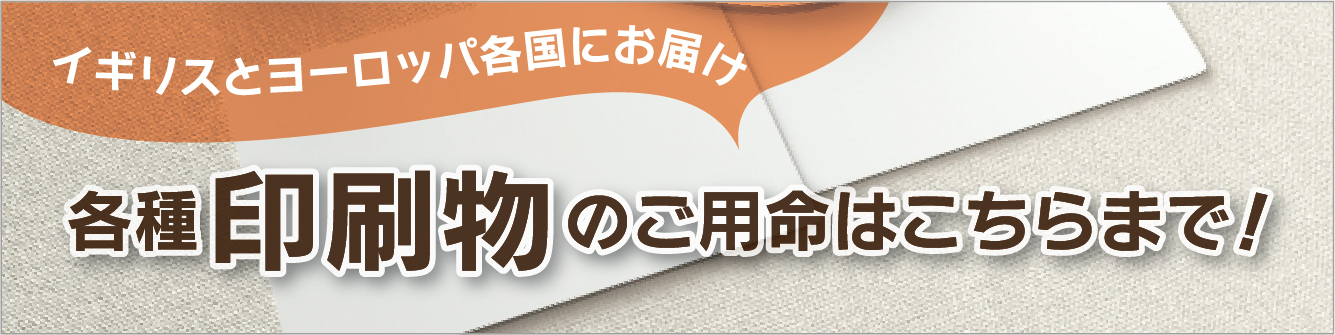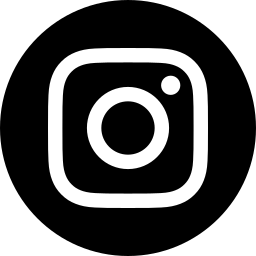スイスの住まい情報
住まいの探し方から契約まで
スイスはヨーロッパの中でもっとも住宅所有率が低い国の一つといわれていますが、農村部では持ち家所有が一般的です。しかし、売買または賃貸可能な物件の種類は豊富で、集合住宅や一戸建て住宅、ファームハウス、さらにはシャトーなど、さまざまな形体の物件があります。
ユーロスタット(Eurostat/EU統計局)の最新データによると、水道・電気・ガス・その他の燃料を含む住宅費をEU平均と比較した場合、住宅費が最も高かったのは、スイス(EU平均比110%増)でした。とはいえ、持ち家であれ賃貸であれ住宅価格は州によって大きく異なり、最も安いジュラ(Jura)の場合、最も高いジュネーブ(Geneva)の約1/4という調査結果もあります。
都市部では特に賃貸物件の需要が高く、見つかるまで平均3~6カ月かかることもあるので、物件探しはできるだけ早めに始めましょう。
不動産会社
高級住宅専門から学生向けまで、多くの不動産会社があります。マルチリンガルのお国柄だけあり、英語を話すエージェントにはことかきません。賃貸市場を把握し、適切な物件を見つけてくれるのは、地元の知識が豊富な不動産会社でしょう。
住まいに関する情報を集めるのには、不動産会社が運営する検索サイトが便利です。フィルターを使って、価格・立地・物件タイプなどの希望の条件に基づいて検索範囲を絞り込むことができます。
不動産会社の一例
Properstar
(担当者が話す言語がわかるページもご利用ください。)
Homegate
Immo Scout24
newhome
immobilier
RealAdvisor
Housing Anywhere
Alle Immobilien
Acheter-Louer
Flatfox
rentola
不動産に特化しているわけではありませんが、スイス生活全般のサポートを行う日本語対応の会社もあります。
トレッソンヌ(Tressonne):ジュネーブエリアに強い
スムーズ・ムーヴ(Smooth Move):スイス移住への確かなサポート
スイス・ワンダーネット(Swiss Wonder Net):主にドイツ語圏での物件検索、内覧、同行通訳サポート
オンライン掲示板
日本人向けウェブサイトの掲示板ページにも、空き部屋情報などが掲載されています。タイミングがよければ、スイス情報.com や、ジュネーブ掲示板 で条件に合う物件が見つかるかもしれません。
物件購入の際に知っておきたい法律
「レックス・コラー法(The Lex Koller Law)」により、非居住者はスイス国内の不動産購入が制限されています。スイス居住許可証を持つ EU/EFTA国民、またはC居住許可証/定住許可(Niederlassungsbewilligung C)を持つ第三国国民、B居住許可証/滞在許可(Aufenthaltsbewilligung B)を持つ人は、居住目的であればスイス国内の不動産を1軒に限り購入できます。購入すると、スイスの土地登記簿に所有者として記載されます
賃貸物件
ジュネーブ、バーゼル、チューリッヒなどの都市部の住まいは賃貸が一般的です。賃貸形態として多いのはアパートですが、地方に行くほどコテージなどの戸建て住宅も増えてきます。
家具付き/家具なし
賃貸物件には、家具付き(möbliert)と、家具なし(unmöbliert)があります。前者は、ベッドやソファーなどが付いており、すぐに生活を始められる物件。後者は、備え付けの収納スペースや白物家電、カーテン、照明以外の移動可能な家具がない物件。大家によって条件は異なりますので、契約前に確認しましょう。
物件を探すにあたって知っておくべきこと
条件に合う物件を見つけたら、迅速に行動しましょう。必要な書類はあらかじめ準備しておき、すぐに申請します。とはいえ、入居できるかできないかは先着順ではありません。また、応募はできるかぎり直接訪問して行うことをお勧めします。物件を見学する際は相手に好印象を与えることはもちろん、応募書類は居住地の言語で記入することが重要です。英語で記入すると審査対象外となる可能性もあります。不動産会社を通した場合、給与基準を満たしているだけでは不十分で、担当者はあらゆる基準に基づいて候補者を絞り込みます。国籍やスイス滞在期間(短いとそこで候補者から外れる可能性あり)、雇用形態、細かいところでは、地域とのつながりなども考慮されます。
プランBを用意しておくと安心ですが、賃貸契約が締結されたら保留中の他の応募をすぐに取り下げないと違約金を請求されることもあるので、気をつけましょう。
契約前に必要になる書類
・成人居住者全員のパスポート/身分証明書
・雇用主からの労働契約書/給与確認書
・労働許可証および居住許可証
・賃貸借申込書(代理店のウェブサイトからダウンロードするか、代理店で入手)
・負債がないことの証明書(ドイツ語 Betreibungsauszug/フランス語 Extrait de l’office de poursuite/イタリア語 Estratto del registro delle esecuzioni)
※国外から移転する場合には不要な場合もあるので不動産会社か大家に確認しましょう。
テナントの権利
テナントは法的に保護された権利を有します。詳細はスイス政府のウェブサイトからPDF形式でダウンロードできます。残念ながら日本語はありませんが、他の12の言語で提供されています。
スイスの法律は一般的に、テナントにとって非常に有利になっています。物件の状態が良好でない場合や、以前のテナントよりも大幅に高い家賃を支払っていることが判明した場合、調停手続きを通じて民間市場で請求されている家賃に異議を申し立てることができます。厳格な家賃規制はないものの、家賃の引き上げに関しては現在の金利に連動していることが決まりです。家賃以外の費用もすべて賃貸契約書に明記されていなければなりません。家主が調停の申し立てを理由にテナントを追い出すことは不法行為です。
ただし家主にも権利はあります。適切な手続きさえ踏めば合法的に家賃を値上げすることは可能です。家主はテナントに対し、値上げの3カ月以上前に通知し、正式な書面に詳細を記載する必要があります。金利の上昇や物件の改修など、家賃の値上げの理由も明記しなくてはなりません。
賃貸契約と敷金
スイスでは、合法的に滞在していれば誰でも住宅を借りることができます。その際、家主とテナント双方の権利と責任を詳細に規定した賃貸契約書を交わさなければなりません。
⚫︎ 賃貸契約
法的には、賃貸契約を書面による契約書で締結する必要はありませんが、そうしておくことをお勧めします。契約書には、賃貸物件の詳細、契約当事者、敷金、月額賃料を記載します。追加費用(例えば、光熱費など)が発生する場合は、それらについても契約書に詳細を記載する必要があります。契約書に家賃以外の追加費用について明記されていない場合は、提示された家賃にすべての合理的な費用が含まれていると想定できますが、テナントの負担額を正確に把握しておくことが大切です。
多くの場合、電話代、電気代、水道代はテナントが負担しますが、家主が平均的な費用の概算額を示してくれることもあります。通常の家賃に加えてすべての光熱費の概算額を毎月家主に前払いするのが一般的です。光熱費の支払いは家主がしますが、テナントに対して毎年詳細な請求書を提示する義務があります。これにより、実際に発生した光熱費と前払い金を照らし合わせて正しいか確認することができ、追加支払いを求めるか、キャッシュバックを受け取ることになります。
スイス政府のウェブサイトでは、賃貸および転貸の両方における賃貸契約書のサンプルを閲覧することができます。あくまでも標準的な内容なため、ニーズに合わない場合には、条項の追加・変更・削除が必要になるので、家主または代理人に契約書の修正を依頼してください。転居の多い駐在員居住者のコミュニティがある大都市では、予定外に移動になるようなケースも珍しいことではありません。退去の通知期間を短縮するための「外交条項」の追加を入れるとよいでしょう。家主が追加条項を受け入れることは義務ではありませんが、交渉の価値はあるでしょう。
⚫︎ 敷金
敷金は最大で家賃の3カ月分を超してはならないという決まりがあります。これは、大家または不動産会社の別口座に保管されるため、事業資金や個人資金になることはありません。敷金は銀行振込にすることが重要です。現金を渡すことは絶対に避けてください。
⚫︎ 契約解約
契約解約については、大家とテナントの双方に対して通知期間を定めておきます。契約書に別段の規定がない限り、通知期間は通常3カ月です。退去が決まったら、書留郵便で家主に通知します。パートナーや他の成人と同居している場合、署名は全員がしてください。通常、テナントは代わりのテナントが見つかった場合にのみ早期に解約ができます。家主との間で未解決の紛争や問題がある場合は、スイス政府の住宅仲裁機関(Federal Office for Housing BWO)に相談しましょう。
⚫︎ 保証金の返還
スイスに限らず世界中でよくある問題として、テナントの退去時に物件に損傷があったことを理由に、大家が敷金を返還しないことがあります。スイスでは、賃貸物件の経年劣化についてはペナルティを科せられることはありません。居住中の物件の維持管理はテナントの責任であるため、賃貸期間中に行った作業や費用の記録は証拠としてしっかり残しておきましょう。大家が退去時に敷金の一部または全額を返還しない場合、物件に費やした時間と費用の記録を提示することで、敷金返還を求めることができます。
大家とテナントの間で直接解決できない問題がある場合は、家主・テナント委員会、または州の調停機関に相談しましょう。住んでいる地域の詳細はすべて、政府のウェブサイトの該当欄に住所を入力することで確認できます。
家の種類
⚫︎ 一戸建て(Einfamilienhaus)
静寂やプライバシーを最大限に提供し、通常は専用の庭が付いているのが一戸建て住宅。風通しが良く、自然光が差し込む設計になっていることが多いようです。しかし、都市のスプロール現象(無秩序かつ無計画に市街地が郊外へ拡大していく現象)から緑地を守ることを目的として作られた土地利用計画規制により、戸建て住宅を建てるための土地が減少しているというのが実情で、住宅価格の高騰もあり、現実的な選択肢ではなくなってきています。
⚫︎ 二戸建て(Doppelhaus)
左右対称の2つの住宅が中央の壁でつながったタイプの戸建て住宅。2つの家族が同じ土地に一緒に暮らしたい場合などにも賢明な選択となるでしょう。
⚫︎ テラスハウス(Reinhenhaus)
3戸以上の戸建て住宅が壁を共有して連なった集合住宅。このタイプの住まいはスイスで長年にわたって高い需要がありますが、近年、新築建設用の土地不足(つまり高騰)となって以来さらに需要が高まっています。戸建て住宅と比較して、約15%のコスト削減という、環境、経済、運用上の多くのメリットがあります。さらに、近隣とのつながりとプライバシーの良好なバランスも期待されます。
⚫︎ 年代物のアパート(Altbauwohnung)
アパートを探す際に「時代物のアパートか、それとも新築アパートか?」で悩む人も多いかもしれません。一般的に、若い世代は時代物のアパートを逆にトレンドと捉え、その魅力と個性を高く評価する傾向があります。新築に比べると家賃が比較的安いのも魅力です。しかし、改装されていないアパートには、床がきしむ、壁が薄い、窓やドアに雨漏りがあるといった欠点もあります。既に改装済みである時代物のアパートも少なくないので、建築年と改装済みかどうかを確認するとよいでしょう。
⚫︎ 新築アパート(Neubauwohnung)
「新築アパートとは〇〇年以降に建てられた物件」という確固とした定義はないものの、1990年代末あたりからオープンプランのリビングの人気が高まり、現在ではオープンプランのデザインは事実上当たり前のものとなっています。これが現代建築のスタンダードであり、象徴となっているといっても間違いではないでしょう。ほとんどの場合、キッチン、ダイニング、リビングルームが一体となって、広々としたスペースを形成しており、その分、内壁や独立した部屋が少なくなる傾向があります。典型的なオープンプラン設計の新築アパートは、似たような日常生活を送る少人数世帯に最適ですが、家族が大きく、個々のニーズや日常生活が多様であればあるほど、伝統的な間取りの方がより実用的だといえるでしょう。
⚫︎ ロフト(Loft)
広々としたインダストリアルな雰囲気を持つロフトアパートは、オープンプランデザインの究極的な形態といえるしょう。内壁はなく天井が高くて、居住空間全体が広い面積に広がっています。2階には部屋が1つだけあるのが一般的です。工場だった建物をロフトに建て替えていた1990年代当時は手頃な価格のアパートでしたが、現在は大規模な改修によって、高価な住宅へと変わってきているようです。
⚫︎ メゾネット/デュプレックスアパート(Maisonette/Duplexwohnungen)
フランス語で「小さな家」を意味するメゾネット。賃貸アパートでありながら、まるで一軒家にいるような感覚を味わえる広さです。メゾネットは少なくとも2階建てで、建物の地下または上層階に位置する場合もあります。上階の居住空間が開放されバルコニーのように見える場合は、「ギャラリーアパートメント(Galeriewohnung)」と呼ばれることもあります。
⚫︎ ペントハウス(Attika)
豪華なタイプのアパートがペントハウス。高層ビルの最上階にあるアパートを指し、特別な設備が備わっていることが多いようです。一般的には、壮大な景色を望む大きなテラスに囲まれており、デザインは、開放的な空間のものもあれば、独立した部屋が複数ある伝統的な間取りのものもあります。
テラス付きアパート(Terrassenwohnung)
部屋のレイアウトや部屋数とは無関係に、テラスを持つアパートを指します。ワンルーム、年代物アパート、ロフトのいずれも、テラスがあればテラスアパートと呼べるでしょう。テラスとバルコニーの違いを理解しておくことも重要です。バルコニーは地上レベルより上にあり、建物の構造から突き出ているのに対し、テラスは必ずしもそうではなく、開放的で通常は地上階または上階に位置しているというのが主な違いです。大きさは関係ありません。
⚫︎ ガーデンアパート(Gartenwohnung)
庭付きのガーデンアパートも人気があります。庭付きの戸建て住宅に住むのは難しいという場合でも、庭付きであるアパートの1階を手頃な価格で見つけることはできるかもしれません。小さな子どもやペットのいる家族やお年寄りには大変魅力のある物件です。
⚫︎ スタジオ(Studiowohnung)
寝室、ラウンジ、オフィス、キッチンなど、主要なリビングエリアの機能をすべて備えた一部屋だけのアパートがスタジオです。通常、レイアウトはシンプルで、キッチンまたは簡易キッチンが部屋に設置され、トイレとバスルームのみが独立した部屋に割り当てられています。廊下はなく、玄関を開けるとすぐリビングエリアになります。ミニマルなインテリアデザインを好む方に最適です。
※スタジオと違い、ワンベッドルームアパートには小さな独立したキッチン、廊下、小さな玄関スペースがあります。
⚫︎ 一軒家の中のアパート(Wohnung in einem Haus)
一般に「多世帯住宅(Mehrfamilienhaus)」と呼ばれ、複数の家族や入居者のために設計された住宅です。少なくとも3つの独立したユニットで構成され、個々のアパートは通常、複数の階にまたがっています。「多世帯住宅」とはいっても、必ずしも家族が住むという意味ではなく、単身者用であったり、学生用であったり、フラットシェアに使われる場合もあります。
⚫︎ 二世帯住宅(Zweifamilienhaus)
2つの独立した(構造的に明確に分離された)居住ユニットで構成されている建物が二世帯住宅(Zweifamilienhaus)。一戸建て住宅に、母屋よりも小さく、二次的な役割を持つ独立したアパート(Einliegerwohnung)が併設されているタイプもあります。最近では、玄関も別々に設けられているタイプもあり、人気が高まってきています。
⚫︎ シェアハウス(Wohngemeinschaft)
特に、学生や若者に人気のシェアハウス/アパート。家賃を抑えたい人には最適のオプションです。学生の多いシェアハウスは、国際色豊かになる可能性も高いでしょう。このような物件は不動産でも扱っている他、学校の掲示板やオンラインプラットフォームでも情報を入手できます。
ゴミ収集のルール
リサイクル率の高さで知られるスイス。住人一人ひとりに自分の役割を果たすことが求められます。ゴミの収集には料金がかかり、その徴収方法は、自治体のゴミ袋を購入する、あるいは市販のゴミ袋に貼るシールを購入するなど地域によってまちまちです。シール購入の場合でも、各州の市町村に特化したものでないとなりません。また、収集ルールを守らないと高額な罰金が課せられることもあります。
最寄りのリサイクルボックスは通常、ガラス、ペットボトル、金属缶、家庭用油などを回収対象としてます。スーパーマーケットにも小さなリサイクルステーションがあり、限られた種類ではありますが、特定の品物を処分することができます。
リサイクル紙は、紐で束ねて特定の収集日に道路脇に置いておくのが一般的ですが、集合住宅だと一般紙用ゴミ箱が設置されていることもあります。地域によっては、古い家具やその他の大型品(自転車など)を回収する日が設けられている場合も。各自治体は、ゴミの収集(収集時間や手順など)とリサイクルに関する情報を、パンフレットの郵送やインターネットを通じて提供しています。在住地域のリサイクルサービスについてもあらかじめ調べておくことが大切です。
また、ほとんどの自治体にはリサイクルセンターがあるので、大量にリサイクルするものが出てきた場合に便利です。センターの規模が大きいほど、回収できる家庭用品や使用済み素材の種類も広く、電化製品、緑の廃棄物、金属製品、家具、さらには動物の死骸まで含まれます。不要だけどまだ使える衣類の処分は、リサイクル拠点に設置されている慈善団体の回収箱に入れましょう。最寄りのリサイクルセンターを探すには、インタラクティブマップをご利用ください。
新しい電化製品や家具を購入する際には、配達時に不要品や壊れた品物を引き取ってくれるサービスがあるかどうか尋ねてみるとよいでしょう。多くは有料になりますが、自分でリサイクルセンターまで運ぶ手間が省けます。また、小売店は使用済み電池の回収を、薬局は不要になった薬や期限切れの薬を引き取る義務があります。