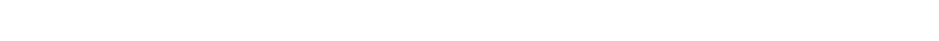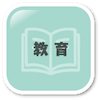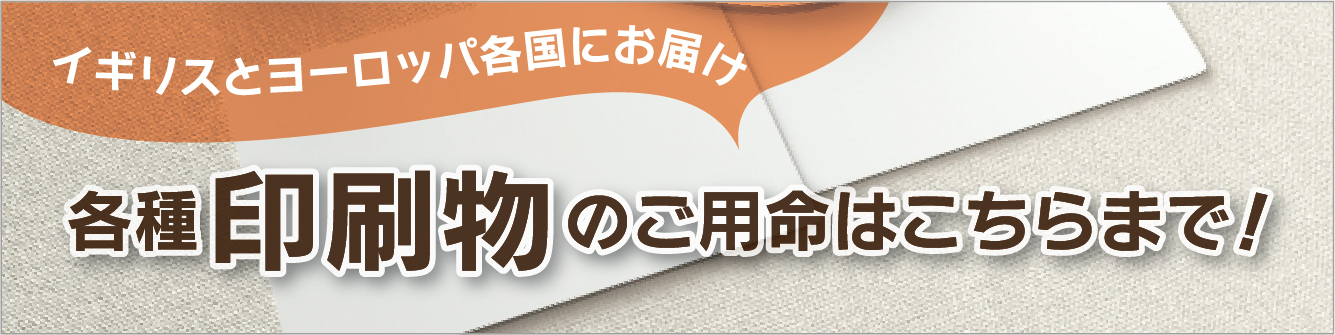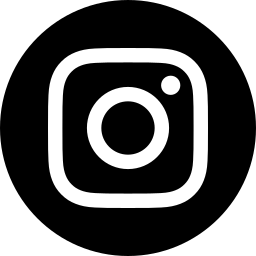オランダの教育
オランダの教育システム
オランダは、子どもの個性や能力に合わせることを重視する教育システムで知られています。初等教育から進路の分岐があり、多様な進学ルートが用意されているのが特徴です。
義務教育と教育年齢
オランダでは、5歳から16歳までが義務教育期間です。ただし、4歳から小学校に入学することが一般的で、ほとんどの子どもが4歳から通学を始めます。さらに、16~18歳の間はパートタイム義務教育があり、学校に通いながら働くことも可能です。
初等教育(Basisonderwijs)
初等教育は8年間(グループ1~8)で構成されます。
・グループ1・2(4~6歳)は、日本の幼稚園にあたり、遊びを通じて社会性や基礎力をつけます。
・グループ3(6歳)からは、本格的な読み書きや算数の学習が始まります。
小学校の最終学年(グループ8)では、「全国共通学力テスト/CITOテスト(CITOTOETS)」を受け、その結果や先生の意見をもとに、中等教育の進路が決まります。
中等教育(Voortgezet onderwijs)
中等教育は、12歳からスタートし、能力や希望進路に応じて3つのレベルに分かれます
1. 中等職業準備教育コース(Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs/VMBO):実習が多く、卒業後は職業訓練校(MBO)へ進学。4年制。
2. 高等一般教育コース(Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs/HAVO):高等専門教育(HBO)への進学を目指すコース。5年制。
3. 大学進学コース(Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs/VWO):6年制。
大学(WO)への進学を目指す最も学術的なコース。
生徒の能力や興味に合わせて分かれるため、早い段階で進路を選ぶ必要がありますが、後から変更(レベルのアップ・ダウン)することも可能です。
高等教育(Hoger onderwijs)
オランダの高等教育は、2つの機関に分かれています:
・高等職業学校(Hoger beroepsonderwijs/HBO):高等職業教育。実践的な専門スキルを学びます。多くの学生がHAVO経由で進学。
・研究大学(Wetenschappelijk onderwijs/WO):大学(研究教育)。より学術的・理論的な教育で、VWO卒業生が主に進学します。
どちらの機関も、ヨーロッパ共通の学位制度/ボローニャ・プロセス(Bologna Process)を採用しており、学士(Baccalaureus)、修士(Master)、博士(Doctor)へと進むことができます。
学校の種類と教育の自由
オランダでは、憲法で「教育の自由」が保障されており、政府がカリキュラムや学校の種類を強制することはありません。そのため、以下のような学校が並立しています。
・公立学校(Openbare scholen):宗教や信条にかかわらずすべての人に開かれた学校
・私立学校(Bijzondere scholen):宗派/イデオロギー学校(Confessioneelonderwijs)と一般特殊学校(Algemeen Bijzonderonderwijs)があり、前者は特定の宗教に基づいた教育を提供し、後者はモンテッソーリ教育(Montessorischolen)やイエナプラン教育(Jenaplanscholen)といった特定の哲学や教育法を持ちます。
すべての学校が政府から平等に資金提供を受けており、小等教育から中等教育までの学費は基本的に無料です。
授業・言語・外国語教育
公用語はオランダ語ですが、英語教育は9歳までは任意ですが、ほとんどの小学校では5歳から開始しています。中等教育では英語の他、ドイツ語・フランス語なども学びます。特に国際都市アムステルダムやロッテルダムなどでは、英語で授業を行う「国際バカロレア(IB)」コースを提供する学校もあります。
教育費と支援制度
小中等教育は基本的に無償で、教科書や教材費も学校が負担する場合が多いです。高等教育は授業料がかかりますが、政府からの奨学金やローン制度(DUO)を利用できます。また、家庭の経済状況によっては教育手当(Kinderopvangtoeslag、Studiefinanciering)も支給されます。
学校生活
制服
オランダでは、ほとんどの学校に制服はありません。生徒は毎日、自由な服装で登校します。学校によっては「適切な服装」ガイドラインがあり、派手すぎる服や露出の多い服は禁止されることがあります。
制服のある学校は、一部のインターナショナルスクールに限られます。
ランチ
オランダの小中学校では、給食制度がないので、子どもたちは自宅から簡単なお弁当(broodtrommel)を持参します。
よくあるランチの内容
・サンドイッチ:パンにチーズやハムを挟んだり、甘いスプレッド(チョコやピーナッツバター)を塗ったもの。
・デザートと飲み物:リンゴやバナナなどのフルーツ、ヨーグルト、スナック、ジュース、水
ランチの過ごし方
・学校によってはランチタイムに一時帰宅する児童もいます(特に近所に住んでいる場合)。
・ランチ後は、校庭で遊ぶ時間がたっぷり取られています。
教科書
・小中学校では、教科書は学校が用意し、貸し出し制になっています。
・破損・紛失すると保護者に請求が来ることもあります。
学用品
・筆記用具・ノート・色鉛筆などは家庭で用意するのが一般的。
・一部の学校では、「文房具リスト(materiaal lijst)」が年度初めに配られます。
宿題
・小学校低学年では宿題はほとんど出ません。
・中学年(グループ5~)になると、少しずつ宿題が出始めます。
・宿題は主に読書、簡単な算数のプリント、語彙・スペリングの練習
最近では、「ClassDojo」「Parro」「Snappet」などのデジタル学習ツールや宿題アプリを使った家庭学習を奨励する学校も増えています。
授業科目・学習内容
・国語(オランダ語)
・算数
・自然・社会(Natuur en maatschappij)
・英語(グループ 7くらいから)
・体育・美術・音楽
科学、技術、工学、数学といった分野を統合的に学び理系人材を育む「STEM教育(STEM-onderwijs)」も年々重視されています。
教師との関係・親の関わり
・先生と保護者の距離が近く、フランクに話せる関係です。
・年に1~2回、保護者面談(oudergesprek)があります。
・学校と家庭の連絡はアプリやEメールが主流。
行事・イベント
・スポーツの日(Sportdag)
・児童書週間(Kinderboekenweek)
・シンタクラース(Sinterklaas)のお祝い
・学校キャンプ(Schoolkamp)
・発表会、演劇、誕生日のイベントなど
子どもが誕生日の時には、クラス全員に小さなお菓子やちょっとしたプレゼントを配る「トラクターツィ(Traktatie)」という習慣があります。
日系教育機関
日本人駐在員の子どもや永住家庭の子どもが日本語教育を継続できるように、いくつかの日本語教育機関があります。主に以下の3つの形態に分類されます。
1.全日制の日本人学校
ロッテルダム日本人学校(Japanese School of Rotterdam)
所在地:ロッテルダム市内
対象:小学1年生~中学3年生(義務教育期間)
・文部科学省の指導要領に基づく日本と同等の教育を提供
・教科書は日本から無償提供され、日本語での授業が中心
・日本人教員が常勤しており、帰国後の編入にもスムーズに対応可能
・英語・オランダ語の授業もあり、現地での生活に必要な言語能力も身につけられる
・スポーツ大会、学習発表会、書き初め、合唱会などの学校行事も日本式
2.補習授業校(週末に日本語を学ぶ)
アムステルダム日本語補習授業校
所在地:アムステルダム市内(教会や現地校の施設を使用)
開催日:週1回、土曜日のみ開校
対象:小学部~中学部、高校部(教科により異なる)
ハーグ・ロッテルダム日本語補習授業校
所在地:アロッテルダム近郊
開催日:土曜に日本語の教科学習を実施
ティルブルグ日本語補習授業校
所在地:アイントホーフェン市
開催日:土曜に日本語の教科学習を実施
マーストリヒト日本語補習授業校
所在地:マーストリヒト市
開催日:土曜に日本語の教科学習を実施
3.現地・インターナショナルスクール内の日本語教育クラスや日本語教室
インターナショナルスクール
アムステルダムやハーグを中心に、オランダ各地に50前後のインターナショナルスクールがあります。
国際バカロレア(IB)や他国カリキュラムを提供する学校の中には「日本語母語話者向け」の日本語クラスを開講している場合があります。週に数時間、日本語で「国語」や「読解」「作文」などを学び、アイデンティティ保持や学力維持を目的としています。
プライベートな日本語教育(家庭教師・塾)
・日本語や日本の教科を教える日本人家庭教師や、オンライン塾も利用できます。
・特にアムステルダム・ハーグ・ロッテルダムなどの都市部には、日本語教育に特化した個人・団体が活動しています。
帰国にあたって
詳細はこちらから