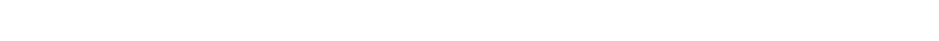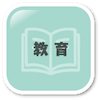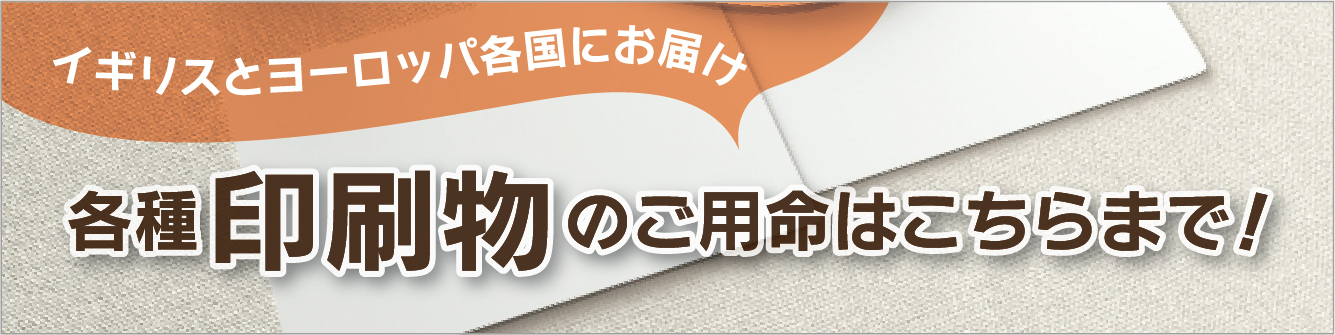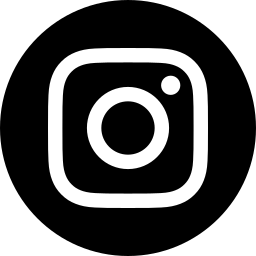スイスの教育情報
スイスの教育システム
スイスにおける教育全般を監督する連邦機関は、「教育・研究・イノベーション省(State Secretariat for Education, Research and Innovation/Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation/SERI)」。連邦機関の他、26州それぞれも教育に関する主要な責任を負っています。そのため、各州には独自の教育局(Erziehungsdepartement)、学年暦、教育体制、教授法、カリキュラムが設けられていますが、カリキュラムについては全国で調整するための協定が締結されています。
年齢別学校の種類
ほとんどの子どもは4歳頃に幼稚園に入園し、正式な教育を受け始めます。義務教育は15歳までで、進学するかどうかは生徒自身が自分で決めることができます。義務教育段階の公立学校においては、小学校から始まり、その後、前期中等学校(基本的には中学校)に進学します。その後、高等学校へ進学進むかどうかの選択をします。
※9年間の義務教育期間に3日連続または不連続で不当に授業を欠席すると、地区行政当局に報告され、保護者には罰金刑か最長2週間の懲役刑が科されます。
スイスの駐在員の子どもたちは私立学校に通う傾向があります。15歳まで教育を受ける義務があることに変わりはありませんが、そのほとんどは18歳まで高校教育を受け続け、国際バカロレア・ディプロマ(International Baccalaureate Diploma/IB)、Aレベル、フランスのバカロレア(Baccalauréat en France/Bac)といった高校卒業資格を得て卒業します。
学齢前の教育
スイスの教育制度では就学前教育は義務教育ではありませんが、多くの子どもたちは4歳頃から幼稚園、または保育園に通い始め、小学校入学前に何らかの教育機関に通うのが一般的です。一部の州では小学校入学前に幼稚園に通うことを推奨しています。その理由は、音楽、工作、ゲームなどを含む遊びを基盤とした学習を通して、子どもたちの発達と社会性を刺激することができるため。外国人の子どもたちにとっては、現地の言語を学ぶ良い機会となり、公立学校に通うという選択肢にもつながります。
幼稚園と保育園のいずれにも公立と私立があり、公立幼稚園は無料。さらに小さい幼児には、保育施設に近い、託児所(crèche)が適しているかもしれません。一般的に、入園を希望する保護者は、幼稚園または託児所に直接申し込む必要があります。
公立小学校
スイスでは総じて教育のレベルが高く、それは公立小学校も例外ではありません。政府が公立教育部門に多額の投資を行っているため、学費は無料です。
各州は独自の教育制度を運営しているため、カリキュラム、休日、教育の細部は州によって多少異なりますが、小学校には4歳から6歳まで通います。一般的に、授業は地域の言語(ドイツ語、フランス語、イタリア語、またはロマンシュ語)で行い、教科には母語と第二公用語、英語が含まれます。科目としては、算数、自然科学、社会科学、人文科学(例:地理、歴史、倫理、宗教)、音楽、美術、体育、保健を学びます。
生徒の評価方法も州によりますが、概ね、年に2回学年報告書を受け取ります。学年末にはテストが行われる場合もあり、これらの評価を元に、進級するか、追加授業を受けるか、あるいは留年するかが決まります。
子どものアフタスクール・ケア
学校の始業時間と終業時間、昼休み時間は、学校、学年、クラス、曜日によって異なります。2人以上の子どもがいる場合は、毎日、子どもたちの始業時間と終業時間がずれる可能性も。水曜日が午前授業のみになるということだけは、スイス全土で共通です。
大都市を中心に、多くの都市には08:00から16:00または18:00まで利用可能な「ターゲスシューレ(Tagesschule)」と呼ばれるデイスクールがあります。しかし、需要が高く順番待ちリストがあることを覚悟しておきましょう。デイリープランにはさまざまなケアユニットがあり、主に、授業前後(午前/午後、午後/夕方のシェルター)や、ランチタイムに利用できます。プランの内容に応じて曜日とモジュールを個別に選択できることが多いようです。
ターゲスシューレに比べると比較的安価なのが「チャイルドマインダー/ターゲスムッター(Tagesmutter)」。一般的に、昼休みや放課後に子どもを預かり、料金は時間単位で計算されます。子どもたちはチャイルドマインダーの自宅で、彼/彼女の子どもたちと一緒に過ごします。
チャイルドマインダーよりも費用はかかりますが、プロのナニーよりは安価なオプションとして、自宅の一部屋と食事を提供し、保護者の留守中に子どもの面倒をみる「オペア」を雇うという方法もあります。オペアの国籍によっては、子どもが外国語を学ぶよい機会になるかもしれません。
経済的に余裕があれば、放課後の保育も提供するバイリンガルスクールやインターナショナルスクールに通うのもよいでしょう。ただし、私立学校は公立学校よりも休みが長いことを覚えておきましょう。
中等教育
スイスの中等学校は、前期中等教育(Lower Secondary Education/Sekundarschule I)と後期中等教育(Upper Secondary Educational/Sekundarschule II)の2段階に分かれています。前期中等教育は義務教育ですが、その後、どのような道に進むかは生徒が自由に選択できます。
・公立前期中等教育
通常11歳か12歳から、3年間にわたる前期中等教育を受け始め、一般的に、ギムナジウム(Gymnasium)またはカントンシューレ(Kantonsschule)と呼ばれる中学校に通います(イタリア語圏のティチーノ州では4年間であることも)。
中等教育のカリキュラムには、通常、地元の言語、第二公用語、場合によっては選択科目として第三公用語、そして英語が含まれます。数学、理科、地理、歴史、公民教育、音楽、美術、体育、家庭科などの科目を履修します。
多くの州では、年に2回、成績と共に進捗状況報告書が生徒に渡されます。それに先立って学年末のテストが行われる場合もあります。その後教師と保護者が面談し、生徒の進級や進学を見据えて生徒の成績について話し合いが行われます。生徒は15歳頃に前期中等教育を修了すると、その後の教育を継続しない選択をすることもできます。この時点では、国家試験や卒業証書はなく、独自の最終試験を実施して卒業の証明書を発行する州もあります。
・公立後期中等教育
14歳から15歳の生徒は、前期中等教育修了後の進路について大きな選択に直面します。職業訓練(Vocational Training/Berufliche Grundbildung)を選択する生徒は全体の3分の2ほどおり、彼らは職場で訓練を受けつつ、週1~2日程度職業学校にも通います。国際的にも高く評価されている制度で、職業訓練のゴールドスタンダードともいわれます。この道を選択した生徒も、素晴らしいキャリアを築き、成功を収めることができます。中には、大手銀行のトップや経済大臣にまで上り詰めた人もいるほどです。
一般教育(Allgemeinbildende Schulen)の道に進むことを決めた生徒のほとんどは、高校に通い、大学進学準備のためのスイス・バカロレア(Maturité Suisses)や国際バカロレア・ディプロマ(International Baccalaureate Diploma/IB)を受験します。一般的に、高校の入学要件は厳しいようです。
一部の州では、12歳前後から高校への入学を申請でき、高校で前期中等教育と後期中等教育の両方を修了することができます。学生は、医療、教育、芸術といった特定の分野で、大学教育と職業教育を組み合わせた「専門バカロレア(Specialised Baccalaureate/Fachmaturität)」を受験することもできます。
高等職業訓練校(Höhere Berufsbildung)
職業訓練を受けディプロマを取得した後は、制度はより複雑に、しかし柔軟になります。進学先の一つとして、高等職業訓練校に進む道があります。企業経営や管理職、あるいは高い責任を伴う専門職活動に必要な知識とスキルを身に付けることを目標としており、特に、連邦職業資格(Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis)は、専門能力開発への道を開きます。これには、連邦職業試験(Berufsprüfungen/BP)、連邦高等専門技術試験(Höhere Fachprüfung/HFP)、そして専門資格が得られる高等職業専門学校(Höheren Fachschulen/HF)の課程が含まれます。理論教育と専門実習が融合されたこの課程は、高度な技術と経営・管理能力を伸ばす訓練を提供する、スイスの特色的な教育制度といえるでしょう。
※連邦職業バカロレアを修了すると大学進学コースに進むことができ、より産業志向の強いスイス応用科学大学(Fachhochschule)に入学することが可能。さらに、「Passerelle(パスレル)」と呼ばれる追加試験に合格すれば、アカデミック大学(Akademische Hochschule)に進学することができます。
スイスの教育制度は柔軟性があり、キャリアに合った勉強をすれば、職業教育と一般教育の間を自由に行き来することができます。
高等教育(Hochschulen)
大学には、「応用科学大学(Fachhochschulen/FH)」、「教員養成大学(Pädagogische Hochschulen/PH)」、「応用科学大学(Universitäre Hochschulen/UH)」の3つがあります。応用科学大学には、州立大学とスイス連邦工科大学(Eidgenössischen Technischen Hochschulen/ETH)が含まれます。大学では、教育の基礎となる基礎研究を行います。より実践志向な応用科学大学と教員養成大学は、応用研究に特化しています。これら3つの大学はすべて、学士号(Bachelor)、修士号(Master)、その他の学位取得につながる学位プログラムを持つ他、継続教育(Weiterbildungen)も提供しています。
継続教育
博士号(Doktorat/PhD)は、修士号に続く大学における第3レベルの学位で、大学でのみ取得可能です。博士論文の内容は科学的な研究論文となります。
私立校
私立の学校は、幼稚園から高校まで一貫した教育を提供していることが多く、子どもに切れ目ない教育を受けさせたい外国人駐在員にとっては、検討すべき選択肢の一つといえるでしょう。スイスの私立校は、大きく分けて以下の3種類があります:
・インターナショナルスクール
幼稚園から高校まで一貫した教育を提供するインターナショナルスクールは、外国人に人気の選択肢。スイスに長期間滞在する、あるいは複数の国のインターナショナルスクールを転校する予定があるという学生にとってはよい選択肢といえるでしょう。授業は、特定の国の教育理念やカリキュラムに沿って行われることが多いようです。アメリカ、イギリス、フランスの教育制度を取り入れている学校の他、日本の教育制度を取り入れたチューリッヒ日本人学校(Japanische Schule in Zürich)もあります(後述)。駐在員家庭の子どもに母国の教育システムに沿った基礎を身につけさせ、将来の帰国を容易にすることが期待できます。
10都市に105校あるといわれるスイスのインターナショナルスクールは、こちらから検索できます。
・宗教系学校(Einrichtungen in Kirchlicher Trägerschaft)
宗教学校も多く存在しています。その多くはカトリック系の学校で、生徒たちは、言語、数学、科学といった基本的な教科に加え、カトリックの教えに基づいた質の高い精神教育を受けています。
・モンテッソーリ教育校(Montessorischule)
医学博士モンテッソーリによって考案された教育法を実施。教師の価値観を押し付けず、子どもの自発性を促すこの教育法を取り入れている学校は「子どもの家」とも呼ばれています。その哲学は、子どもたちの高い創造性と自立心を育むことに重点を置いているといわれます。
私立校のリストはこちらから検索することができます。
学校生活
制服
ヨーロッパの皇室の子女が通う「レマニア・ヴェルビエ国際学校(Verbier International School)」のような超一流私立学校を除けば、制服を導入している学校はほとんどありません。
とはいえ、制服導入に関する話題は定期的に持ち上がります。教育は各州の責任となっているスイスでは、これまでも州議会で公立生徒に制服を着用させるかどうかの動議が出されてきましたが、制服着用を強制するのは「後退」と見なされ、否決されました。
「制服の歴史的ルーツは、平等主義の理想を表現するための軍服にあり、私立学校においてはエリート校と公立校の視覚的な区別のために導入され、どちらも、民主的で多元的な社会における現代のスイスの公教育制度には合致しない」という、ドイツ語圏スイス教師連盟の理事の言葉もありました。その一方で、私服だと流行りの服を着ないと仲間に入れないというプレッシャーがあり、そのために借金をしたり、露出度の高い服や不適切なスローガンが書かれたジャンパーを着たりする生徒がいるという問題もあり、制服は分断と社会的格差を減らすためのよい手段と主張する制服支持者もいます。
スイスの一般的な考え方としては、制服着用のプラス面よりも、個人の自由に対する侵害というマイナス面の方がはるかに大きいようです。だからといって何を着てもよいというわけではなく、私服に関する規定を定めている州もあります。
ランチ
子どもたちは、午前中に小腹が空いたときのためにフルーツやスナックを持参しますが、ランチは基本的に毎日帰宅して自宅でとります。州によって多少の違いはあるものの、学校には2時間程度の昼休みがあり、4歳でも14歳でも、子どもたちは11:45から12:15の間に帰宅し、13:15分から13:30の間に再び登校します。
スイス人の多くがそうであるように保護者が地元で働いている場合にはそれほど問題にはなりませんが、勤務先と自宅が離れていたり、子どもの昼休みに合わせられない時間帯で労働したりしているケースが多いのも事実。バーゼルやチューリッヒなどの大都市であれば、ランチケアやアフタースクールケア(Hort)など、学校時間外の保育サービスが充実していることも多いでしょう。地方都市であっても、運がよければランチクラブ(Mittagstisch)を見つけられるかもしれません。しかし、そのような施設が必ずしも学校と同じ建物内にあるとは限りません。学校と距離がある場合、子どもたちをいかに安全にその施設に行かせるかは保護者の責任となります。
※ランチクラブの料金は、自治体/ゲマインデン(Gemeinden)によって大きく異なります。
中等教育以上の年齢になると、弁当を持参したり、近所の小売店やファストフード店まで買いに行ったりするようになります。弁当を温められるよう電子レンジを設置している学校もあるようです。大学では、手頃な価格で毎日異なるメニューを提供するカフェテリアがあることが一般です。
教科書
義務教育の教科書は無償で提供されますが、高校では自己負担となります。教科書は学習体験の重要な要素であるため、授業初日までにすべて揃えておかねばなりません。教科書を販売する本屋である Bücher-Brocky や Orell Füssli では、安価で古本の教科書を購入することもできます。
※教育制度は州ごとに決定権があるため、義務教育期間や教科書に関する詳しい規定は州によって異なります。
日本国籍を持つ児童は、日本の義務教育教科書を無償で受け取ることができます。在スイス日本国大使館に問い合わせましょう(https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyoiku.html#教科書の無償配布について)
宿題
スイスでは、宿題の内容や量は、学年、学年レベル、教科、そして個別指導のアプローチによって異なります。低学年の宿題は学校生活に組み込まれることもあり、授業の終わりに指定された時間枠で行われる他、授業中に自主学習ユニットの形で行われることもあります。宿題は、保護者の過度な介入なしに子どもが自力で課題をこなすことが期待され、早期に自立心を育む方法の一つとなっています。
中学生になると、授業時間外に予習・復習のための宿題をこなすのにより時間を費やすようになることが多いようです。
さらに、学年が上がるごとに増えていく宿題や課題、プレゼンテーション、エッセイなどをこなしながら、アルバイトや社交活動もするとなると、かなりのプレッシャーがかかります。そんな状況を支援する専門的プラットフォームやサービスを利用する生徒もいます。その内容は、生徒と家庭教師をオンラインでつなぐ個別指導から特定の課題支援まで多岐にわたります。さまざまな科目や学力レベル、さらには学校の種類や大学に合わせたサポートを見つけることができます。
誕生会
子どもが小さいうちは、学校や近所の友だちを招待して誕生日を盛大に祝います。スイスには、好みや予算に合わせた幅広い会場やアクティビティがあります。アドベンチャーパークやホリデーパーク、博物館、公園、屋内外のコミュニティセンター、動物園など、誰もが楽しめるものが見つかるでしょう。
天候が変わりやすいお国柄のため、季節に合った会場とアクティビティを選ぶことが重要です。子どもの年齢層を考慮した予算を決め、飲食が含まれるパッケージが提供されていない場合には、主催者が人数分の子どもと保護者の食べ物や飲み物を用意しておきましょう。人気の会場や業者は早くに予約が埋まってしまうことがあるので、計画は早めに立てましょう。
家族手当(Familienzulagen)
誕生してから16歳まで(健康上の問題で就労していない場合は20歳まで)の子ども1人につき月額215スイスフランが、25歳までの就学中の子どもには月額268スイスフランの手当が支給されます。
一部の州や一部の雇用主の元では、手当の額がさらに高額になる場合があります。また、出産や養子縁組の際に特別手当が支給される場合もあります。
保護者は、子ども1人につき1つの手当を受け取る権利があります。保護者が2人いて両方が就労している場合は、保護者1人にのみ支給されます。
また、就労中、自営、無職のいずれであっても課税所得が低い人は、家族手当が受給できます(受給資格の基準額は州によって異なります)。失業者として登録されている場合、家族手当が受給できない代わりに失業手当の補足給付(Zuschlag zum Arbeitslosentaggeld)を受けることができます。
※海外の労働者や季節労働者も、一定の条件の下において家族手当を受給できます。
家族手当は自動的に支給されるものではなく、申請をする必要があります。被雇用者は、雇用者に手当の受給手続きを依頼します。申請は雇用者の家族手当補償基金(Familienausgleichskasse)に送られ、承認されると、毎月給与と共に手当が支給されます。
自営業の場合は自分の家族手当補償基金に申請を、無職の場合は州補償事務所(州OASI補償事務所が管理)に家族手当(Kantonalen Familienausgleichskasse)を申請する必要があります。
注:家族手当の申請を忘れたり、申請できることを知らなかったという場合には、最大5年前まで遡って申請することができます。
日系教育機関
スイスには、日系、あるいは日本人を多く受け入れる教育機関がいくつか存在します。
1. 日本人学校
チューリッヒ日本人学校(Japanische Schule in Zürich)
日本政府公認の在外教育施設。チューリッヒ日本商工会から選出された委員により運営されています。月曜日から金曜日まで、日本の小学校や中学校と同等の教育を受けます。日本の教科書を使用し、日本の学習指導要領に準拠した授業が行われています。
チューリッヒ日本人学校補習授業校(Japanische Schule in Zürich, Samstagsschule)
日本文部科学省学習指導要領を基とする国語科授業では、幼稚部、小学部、中学部、国際部、高等部まで一貫した教育を行う他、継承語として日本語を学ぶ国際部も併設。授業は土曜日に行われます。
ジュネーブ日本語補習学校(École Japonaise Complémentaire de Genève)
日本政府の在外教育施設として認可された補習授業校。国語や算数・数学を中心に日本の教科書を使用しています。対象は、ジュネーブとその周辺に住む幼稚部、小学部、中学部、高校部までの日本人子女。授業日や時間は学部によります。
2. 継承日本語教育機関
おひさま日本語学校(Ecole japonaise OHISAMA)
同じ境遇にある子どもたちが日本語や日本について学び、共有できる場を提供。未就学の子どもが日本語で遊べる「プレイグループ」、小学校低学年レベルの日本語が学べる「学習クラス」、学習クラスを卒業後も日本語の勉強が続けられる「チャレンジクラス(オンライン講習あり)」を提供しています。
住所:Route de Préverenges 16, 1027 Lonay(14U – Eglise Evangélique de Lonay 内)
ヌーシャテル日本語学校(École japonaise de Neuchâtel)
子どもたちの日本語の習得と日本文化に対する理解を深める場を提供することを目的とし、日本人有志により設立。2013年にヌーシャテル州LCO(母国語文化教室)準認定校となり、2019年以来LCO正式認定校として活動しています。
住所: Av. de Bellevaux 52, 2000 Neuchâtel
パンフレットのダウンロードはこちらから
バーゼル日本語学校(Japanische Schule Basel)
1985年に創立された非営利団体「バーゼル日本語学校協会」が運営。現地校に通う児童・生徒に、日本文化を含めた継承語としての日本語を教えています。2003年度にバーゼル教育庁のHSK(継承語及び継承文化授業)の認定校となりました。
幼児部住所: Delsbergerallee 29, 4053 Basel
小学部住所:Schulhaus Gartenhof, Lettenweg 30, 4123 Allschwil
中高学部 :Berufsfachschule Basel, Kohlenberggasse 11, 4052 Basel
ベルン日本語教室(Japanische Schule Bern)
1995年、スイスの首都ベルンにおいて、日本人・日系人の子どもを対象に設立された非営利団体。首都近郊のドイツ語圏とフランス語圏の現地校に通う子どもたちに、日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の四技能を教える他、異文化理解や多角的な視点を持って複言語複文化社会の一員として柔軟な思考を身につけさせることを目指す学校です。
住所: Schulhaus Pestalozzi, Weissensteinstrasse 41, Bern, 3007
ルツェルン日本語学校(Japanische Schule Luzern)
スイスの現地言語で学校生活や社会生活を送る一方、親子間で話される日本語での相互理解を深め、よりよい関係を築き、日本語、日本という国や文化・社会に関する興味と知識を深める継承日本語教育を目的とした学校です。
住所①:Schulhaus Höfli, Oberdierikonerstrasse 25a, 6030 Ebikon
住所②:Schulhaus Feldmatt, Rankstrasse 2, 6030 Ebikon
ローザンヌ日本語学校(École japonaise de Lausanne)
円満な親子関係、ひいては子ども自身のアイデンティティの形成に大切な継承語を学ぶ学校。2歳から満5歳までの児童にはひらがなを教え、日本の遊びを楽しむ「子ども会」も提供しています。
小学部住所 :Collège du Vieux-Moulin, Route des Plaines-du-Loup 6, 1018 Lausanne
子ども会住所:Paroisse de Bellevaux, Route Aloys-Fauquez 21, 1018 Lausanne
3. インターナショナルスクール
スイス公文学園高等部(Kumon Leysin Academy of Switzerland/KLAS)
国際教育・バイリンガル教育・人間的成長という普遍的な教育方針を掲げる全寮制学校。体験授業やアクティビティ体験、また異文化を肌で感じることのできる近隣都市への訪問などが盛り込まれたサマースクールも実施しています。
住所:Route de Versmont 6 CP110, CH-1854 Leysin
コレージュ・デュ・レマン(Collège du Léman International School)
約110〜120カ国から生徒が集まる国際都市ジュネーブ郊外の学校。アメリカ卒業資格が得られるAP(US High School Diploma)、国際バカロレア(International Baccalaureate)、フレンチバカロレア(French Baccalauréat)、イギリス中等教育修了資格となるIGCSE、スイス・マチュリテ(Suisse Maturité)の5つアカデミックプログラムの中から卒業資格を選択できます。日本人生徒も多く日本語のウェブサイトもあり。
住所:Route de Sauverny 74, CH-1290 Versoix, Geneva
ブリアモン・インターナショナルスクール(Brillantmont International School)
130カ国以上から生徒が集まる学校環境の中、世界に通用する全人教育を通じて、国際性とバランス感覚が日常的に習得できる全寮制の学校。進路に沿った多様な教育プログラムと、スポーツやボランティアなどの充実した課外活動が両立し、世界トップクラスの大学への進学実績も豊富です。定期的にスイス留学・サマースクールセミナーを開催。日本語の公式ウェブサイトもあります。
住所:Route de Sauverny 74, CH-1290 Versoix, Geneva
帰国にあたって
詳細はこちらから